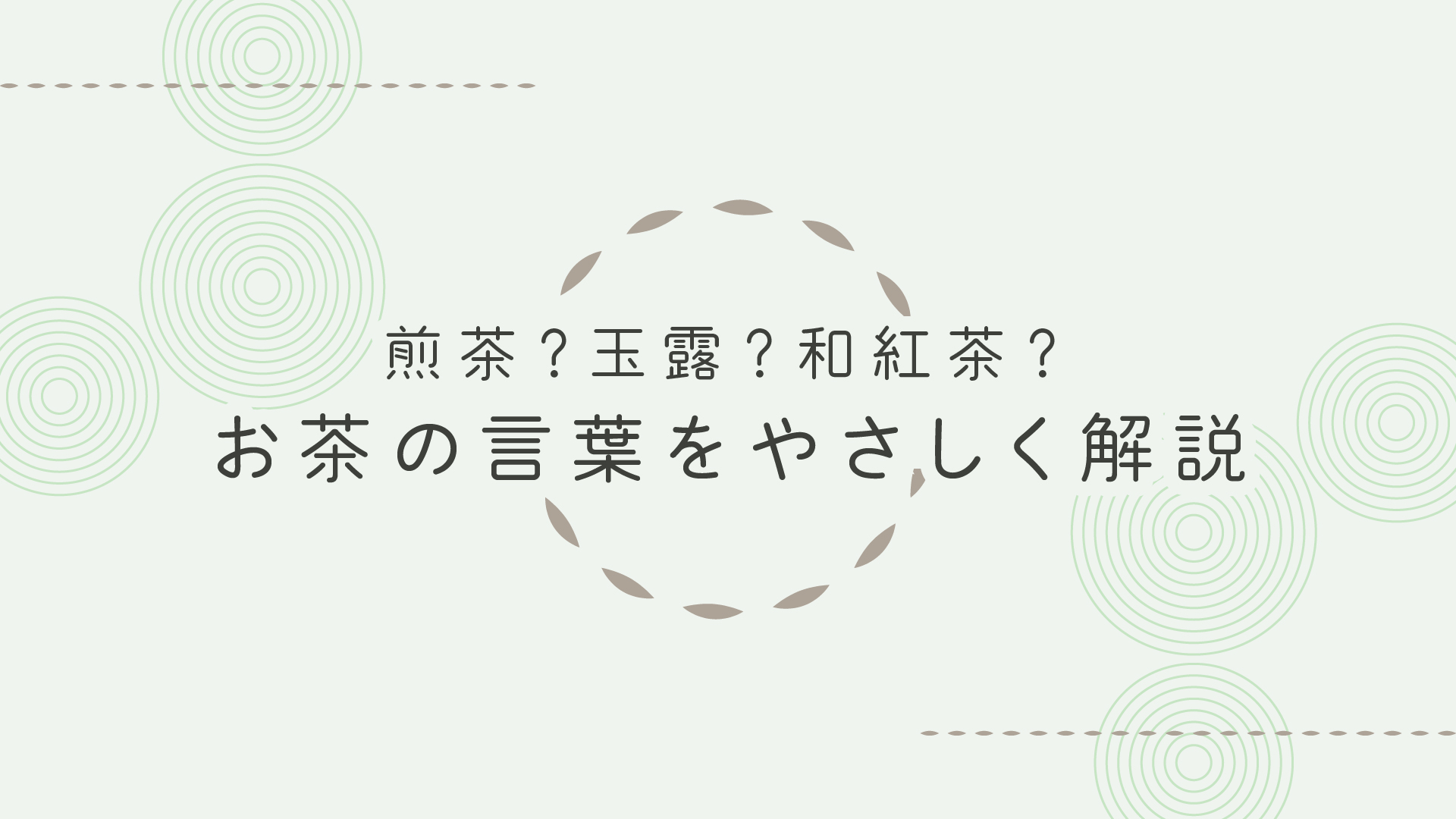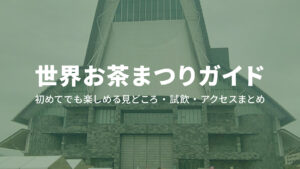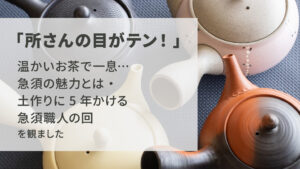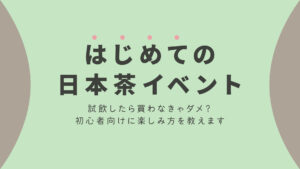日本茶を飲んでみたいけれど、「煎茶」「玉露」「番茶」「和紅茶」など、名前が多くてよく分からない…そんな声をよく耳にします。お店やカフェで注文するときに戸惑ったり、プレゼントで選ぶときに迷ったりする方も多いのではないでしょうか。この記事では、日本茶に詳しくない方でも理解できるように、代表的なお茶の名前をやさしく解説します。
煎茶(せんちゃ)
日本茶の中で最もよく飲まれているのが煎茶です。緑茶といえばまず煎茶を思い浮かべる方も多いでしょう。煎茶は茶葉を蒸して揉みながら乾かすことで作られます。香りと渋み、そしてほどよいうま味がバランスよく味わえるのが特徴です。
日常的に飲まれることが多く、湯呑みに入れれば食事のお供にも、おやつタイムにもぴったり。お湯の温度を少し下げれば甘みが引き立ち、熱めでいれるとすっきりとした渋みを楽しめます。普段のお茶として最初に手に取るなら、煎茶が基本となります。
玉露(ぎょくろ)
玉露は高級茶として知られるお茶です。栽培方法が特徴的で、収穫の20日前後から茶畑に覆いをして日光を遮ります。日光を控えることで、渋みの成分が抑えられ、代わりに甘みやうま味成分が豊かに蓄えられます。その結果、とろりとした甘みとうま味が強調された、贅沢な味わいになります。
飲むときはお湯をかなりぬるめ(50〜60度程度)にして、じっくり時間をかけていれるのがポイントです。少量でも深い満足感があり、特別な日の一杯として選ばれることが多いお茶です。
H2 ほうじ茶(焙じ茶)
ほうじ茶は、煎茶や番茶を強火で炒ることで作られます。炒ったときに立ち上る香ばしい香りが特徴で、さっぱりした飲み口になります。渋みが少なく胃にもやさしいため、食後や就寝前にも安心して飲まれることが多いお茶です。
カフェイン量も比較的少なめで、小さなお子さんからお年寄りまで幅広い世代に親しまれています。リラックスしたいときや食事の後にぴったりの一杯です。
番茶(ばんちゃ)
番茶は「晩のお茶」という意味ではなく、煎茶に比べて遅い時期に摘まれた茶葉から作られるお茶です。葉が大きめで、香りや味わいは軽やか。地域によっては日常的に番茶がよく飲まれています。
クセが少なく飲みやすいので、大人数でのお茶会や食事のときに出されることも多いです。普段使いの親しみやすいお茶、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
和紅茶(わこうちゃ)
和紅茶は、日本で栽培された茶葉を使って作られた紅茶です。緑茶と同じ茶の木からできていますが、加工の仕方が違うため紅茶になります。海外の紅茶に比べて渋みが穏やかで、やさしい甘みを感じられるのが特徴です。
そのままでも飲みやすいですし、ミルクやはちみつを合わせても相性抜群です。日本生まれの紅茶なので、日本の和菓子や洋菓子どちらにもよく合います。紅茶好きの方にもぜひ試していただきたい一杯です。
まとめ
「煎茶」は毎日の定番、「玉露」は特別なごちそう、「ほうじ茶」は香ばしくてやさしい味わい、「番茶」は普段使いのシンプルなお茶、そして「和紅茶」は日本生まれのやさしい紅茶。
名前を整理して覚えるだけで、お茶選びがぐっと楽しくなります。カフェでの注文やお店でのお買い物のときも、自信を持って選べるはずです。まずは気になる名前のお茶をひとつ試してみて、自分の好みを探してみてください。